有機化学I第1回
<-- 2023年回答のうち誤答の正しい分類--> <--過去の回答例はこちら。以下の質問は、「Q&A」に回答があります。
(質問)(化学を専門としないのに)有機化学を学ぶことの意義は何か?
(質問)イオン性物質と分子性物質の区別の仕方は?
(コメント)詳しくは、上の「過去の回答例」のページの冒頭の説明をご覧下さい。
同様の組み合わせであっても、「酸化~」で始まる名前を持つ物質の中には、イオン性物質ではなく無機高分子に分類されるものもあります。
(質問)レシチン(リン脂質を含む脂質製品の総称)は分類できますか。
(質問)着色料はどの分類になりますか?
(質問)「無水ケイ酸」は物質名か?(無機化学命名法)
(質問)有機物の定義は?
(コメント)Q&Aのページのほか、テキストの第1章にも説明があります。
(質問)分子性物質と高分子物質の違いは?
(質問)「有機化学I」では生物体に関する物質や反応について学ぶことはできますか。
(質問)「果糖」を「フルクトース」と呼ぶときがあるが、これはどうしてか。
(質問)有機物の名前からおおよその機能を推測することはできるか。
(質問)演習課題第2回(3)について、「元素組成から分子式を区別する」とはどういうことか。
(質問)結合の極性の有無はどのように判断すればいいのか。
(質問)形式電荷を求めることにより何がわかるのか。
(質問)オクテット則とは何か?
3-1質問2 結合の回転のしやすさは性質にどのような影響を与えるのか。
(これから学びますが,結合の回転が起こりやすい分子は、一般に分子の形が変わりやすいです。)
3-2質問1:ひずみエネルギーの計測はどのように行われたのか。Good Question!
回答:たとえば、生成エンタルピーの実験値を、ひずみがない分子と比較することで推算することができます。
3-2質問2:ひずみエネルギーを算出する公式はあるのか。Interesting!
回答:推算する方法はありますが,炭素数を代入すれば答えの出る公式のようなものはありません。
Q. 「非結合性軌道 nonbonding orbital」とは何か。「反結合性軌道 antibonding orbital」とはどう違うか。
質問:命名法の表3の接頭語にしかなれない官能基には、なぜ優先順位がないのですか? Good Question!
A:名前を付ける際に優先順位をつける必要がないからです。規則では、接頭語にしかなれない置換基は、名前を付けるときに基名のアルファベット順に並べるためです。
質問:σMOへの寄与が大きいとはどういうことか。(内容は物理化学)
A: σMOはAOを組み合わせて作られる(2章〜3章)。組み合わせるときに,σMOとのエネルギー差の小さいAOのほうが,σMOの電子雲の形に大きく影響を与えるので「寄与が大きい」という。πMOでも同じ。
質問:可能な水素結合の数を化学式から判断することはできますか。また、判断するのに必要なものはありますか。 Good Question!
A: 分子式では判断できません。構造式なら判断できます。
水素結合の供与体(D)であるHの数と受容体(A)である非共有電子対の数が必要です。
質問 授業資料中の図.炭素数および水素結合と沸点のRHが、炭素数1~5の範囲で他と比べて沸点の上がり方が急なのはなぜか。Good point!
A: 気体分子運動論(高校物理・化学)によると,同じ温度では分子の平均運動速度(vav)は分子の質量(m)の1/2乗に反比例します(vav ∝ √(1/m) = m-0.5)。分子質量(m)は概ね炭素数と共に直線的に大きくなります。一方,直鎖の炭化水素基では,分子間力は炭素数と共にほぼ直線的に大きくなります。これらのことが沸点に影響を与えている可能性があります。炭化水素(RH)以外の場合には、官能基の存在により分子間力が大きくなるために、炭素数の違いによる上のような効果が緩和され、炭素数に対する沸点の変化が小さくなると考えられます。
質問 水以外の溶液中やイオン液体の中の酸解離定数も同じ定義ですか。Important!
回答:同じです(大きさは異なる)。化学Aで学んだように,Brφnsted(ブレンステッド)の酸・塩基の考え方は,水以外の溶媒中でも成り立ちます。
質問 構造異性体の書き方のコツはありますか? Good Question!
A: 飽和炭化水素を例として記します。まず炭素数から考えられる母核(命名法のときと同じ。直鎖・環)の種類をできるだけ見つけます。そして,各母核について,側鎖(枝分かれ)の位置と種類が異なる構造をできるだけ描きます。最後に,同じ構造が重複していないか検討します。迷ったときは,命名法規則に従って命名します。同じ名前になるものは(当然)同じ構造です(BIOVIA Drawで描いていると容易にチェックできます)。有機化学のページのQ&Aの「結合と構造」(6)もご覧下さい。
Q.次の質問への回答はQ&Aのページに掲載されています。
(Q) 問13(1) に関連して、C4H6の異性体の一つ、![]() のIUPAC名を教えて下さい。
のIUPAC名を教えて下さい。
(Q) カルボン酸のカルボンはどういう意味か?
質問への回答
Q. 配座異性体間の変化(結合の回転、シクロヘキサンの環反転など)を起こすためのエネルギーはどこから得られるのか。
A. 良い質問です。結合の回転が起こるためには、十分な運動エネルギーが分子の一部に与えられる必要があります。これにはいくつかの可能性が考えられます。
一つは、分子のもつ内部エネルギーからです。これは分子内のいろいろな運動エネルギーの総和であり、エネルギーは相互変換できますので、時間と共に運動の様子は変わっています。
もう一つは、外部から分子に与えられるエネルギーです。たとえば、他の分子との衝突により得られるエネルギーが考えられます。液体中や気体中では、分子はたえず他の分子と衝突しており、そのたびに互いにエネルギーをやり取りして、各分子のもつ内部エネルギーは変化しています。
(以下は「物理化学」の内容)
分子のもつ運動には、並進運動(いわゆる分子運動)および分子全体としての回転運動のように分子の形の変化を伴わない運動と、分子内の各結合の振動(伸縮・変角)・回転およびシクロヘキサンのイス形の環反転や窒素の非共有電子対の反転のように分子の形の変化を伴う運動とがあります。単原子分子では並進運動だけを考えれば良いですが、原子数が増えて分子の構造が複雑になるにつれて、多種多様な運動が同時に起こっています。
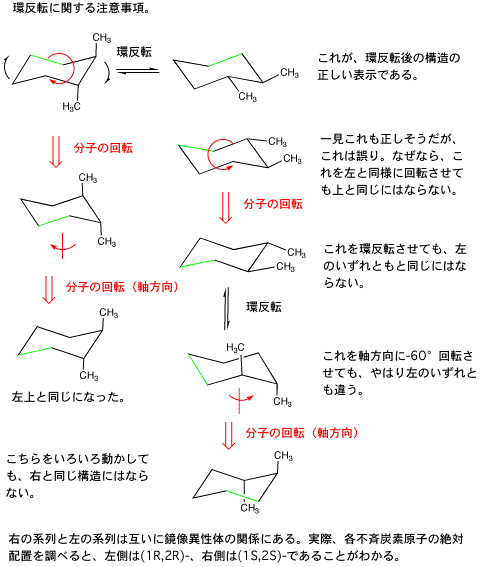
1-ethyl-2-methylcyclohexane などでも事情は同じ。
しかし、cis-1,2-dimethylcyclohexane では事情が異なる。